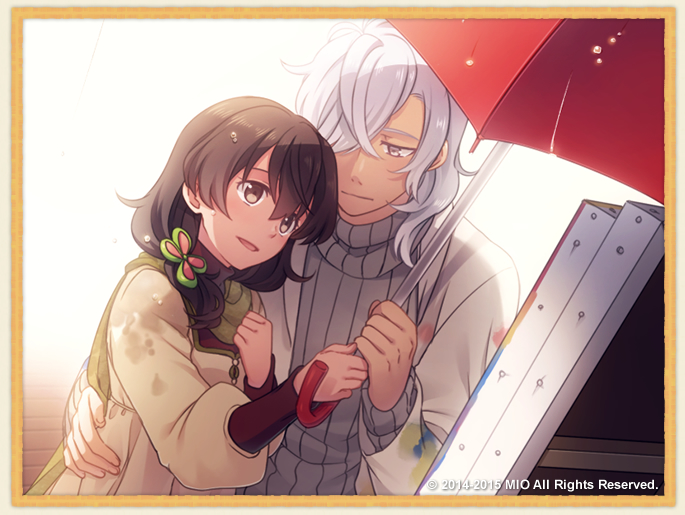
雨音弾む
結局、夕方になっても雨が止むことはなかった。
傘に入りきらない肩が、すっかり濡れて冷えている。
千紘
「もうすぐ夜だから、それまで、どうにか」
傘を何度も持ち直しながら、私は耐える。
指は、すっかり傘を持つ形に固まっていた。
千紘
(あと少し……あと……もう少し……)
そして、ようやく日が沈む時間。ふと気づくと、いつしか雨足は弱まり始めていた。
途端、私の腕の中の画集が震える。
そのまま、あっという間に樒さんの姿になると、一緒に傘を持ってくれた。
千紘
「樒さん」
樒
「ありがとう……ずっと、守って……くれたんだ」
黙って首を振ると、体を抱き寄せられる。
樒
「こんなに……冷たくなるまで……ずっと」
樒さんの声が、憂いを帯びる。
千紘
「大事な絵だから……」
本心からの言葉だった。
自分ひとりで絵を動かせないと思ったとき、こうすることに迷いはなかった。
樒
「こんな絵……君が、風邪をひいたり……するくらい……なら、濡れても……よかった」
絞り出すような声に、じんとする。
私を大事に思って、心から気遣ってくれている響きがそこにはあった。
千紘
「私は、これくらいなら大丈夫です」
樒
「冷たい」
ぎゅ、と樒さんの手に力がこもる。
千紘
「でも、今は樒さんが、あたためてくれてます」
樒
「うん。あたためる」
私の腰に回された手が、ぐい、と私を抱き寄せ、それに素直に身をゆだねる。
私は樒さんを、その体温や鼓動さえわかるくらいにとても近くに感じた。
こんなにも近くに、誰かの意志ある腕を感じるのは初めてで、鼓動は速まるばかりだ。
否応なしに恥ずかしい気持ちは増すのに、離れがたい。
雨の音が傘の上に落ちている。
その音が今は弾んで聞こえて、不思議な感じがした。
私たちは寄りそったまま、一樹さんと棗さんが手伝いに来てくれるまで佇んだ。
ふたりで絵を守りながら、相合傘の下で身を寄せ合って……。
それは雨の冷たさに凍えるような寒い時間じゃない。
とろけるような甘さが熱にとけて滲んでいくひとときだった。